パックセンターとは?自社運営と外注利用の比較や自社運営する際に役立つ製品を解説
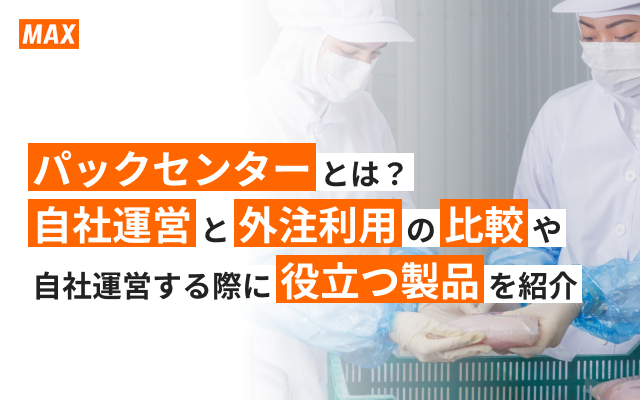
「パックセンターって何?」
「パックセンターは自社運営と外注利用だとどっちが良いの?」
パックセンターは、商品を迅速かつ効率的に包装し、適切に市場へ流通させる重要な役割を果たす施設です。特に食品業界においては、パックセンターが果たす役割は非常に大きく、消費者の手元に新鮮な食品が届けられるプロセスを支えています。
この記事では、パックセンターの基本的な役割や、自社運営と外注利用の違い、それぞれのメリットについて詳しくご紹介します。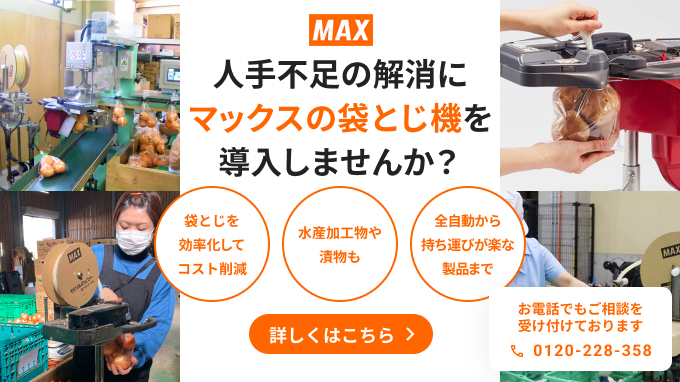
1.パックセンターとは?
パックセンターとは、商品や食品を効率的に包装し、市場へ流通させるための施設で、生産者から届いた商品を包装し、小売業者や最終消費者に向けて出荷します。食品業界においては、商品が消費者に届くまでの時間が品質に大きく影響するため、パックセンターでの迅速かつ正確な作業が求められます。さらに、包装工程には食品の鮮度を保つための工夫や、安全性を確保するための衛生管理が重要です。
(1)卸売業との違い
卸売業は、生産者から商品を仕入れ、包装やその他の処理を行った後、小売業者へ配送する業種です。商品の流れはパックセンターに似ていますが、卸売業者の主な役割は、生産者と小売業者の間に立ち、取引を円滑に進めることです。
一方、パックセンターは商品の包装や加工を専門的に行い、消費者に届く最終的な形で販売店舗へ効率的に配送することを目的としています。パックセンターは品質や作業性に特化したサービスを提供し、より付加価値の高い商品を生み出す役割を果たします。
(2)インストア加工との違い
インストア加工とは、商品の包装や簡単な加工を、販売する店舗内で行う方法を指します。この方法は、各店舗に必要な機材や人材を設置する必要があり、店舗の数が多い企業ではコストが大きくなりがちです。インストア加工の利点は、商品がすぐに店舗に並べられることで、包装にかかる時間を短縮できる点です。しかし、店舗ごとの作業負担や品質のばらつきが発生しやすいというデメリットがあります。
パックセンターは一箇所に設備や人材を集約するため、全体的なコスト削減が期待できるだけでなく、包装の品質管理も一元化できます。
2.パックセンターを自社運営する場合と外注利用する場合の違い
パックセンターを自社で運営するか外注利用するかは、企業の戦略や規模によって大きく異なり、主な違いは以下となります。
| 自社運営 | 外注利用 |
| 初期投資が高い | 初期投資は不要 |
| 長期で利用すれば、ランニングコストは下がる傾向にある | 利用量に応じてコストが発生し、長期的には高額になる可能性がある |
| 品質は自社で柔軟に管理・改善が可能 | 品質は相手依存となるので柔軟な対応が難しい |
| 専門的な人材の雇用や教育が必要 | 専門的な技術や知識を利用可能 |
| 繁忙期・閑散期の人員調整が必要 | 利用量に応じて柔軟に調整可能 |
自社運営の最大の利点は、コスト管理と品質の柔軟性です。長期的には外注費用に比べてランニングコストが下がる傾向にあり、自社製品に最適化された包装を提供することができます。
一方、外注利用は初期投資が不要であり、専門的な技術やノウハウによる高い品質の作業を依頼できるので小規模の企業や、パック作業以外の業務に専念したい企業が利用する傾向にあります。しかし、長期的に見るとコストが増加したり、品質が外部依存になってしまう可能性があります。
最終的に、自社運営か外注利用かの判断は、企業の規模やニーズ、包装作業の複雑さ、求められる品質水準、コストの許容範囲などを総合的に考慮して行うことが重要です。
3.パックセンターを自社運営する主なメリット
パックセンターを自社運営するメリットは以下になります。
- 長期的に見ればコスト削減ができる
- 包装の品質を向上できる
- 柔軟な対応が可能になる
それぞれご紹介していきます。
(1)長期的に見ればコスト削減ができる
パックセンターを自社で導入する際には、初期費用として施設や設備、人材の確保が必要となります。しかし、長期的に見れば、店舗数が増えるほどコスト削減効果が大きくなります。
またパックセンターで一括して包装業務を行うことで効率が上がります。さらに、包装作業を専門のスタッフが行うことで品質の安定化も図れるため、全体の生産性が向上します。
(2)包装の品質を向上できる
自社でパックセンターを運営する場合、包装の品質を自社の基準に合わせて細かく管理できるという点が外注利用との大きな違いです。外注利用では、委託先の品質基準に依存するため、自社の要望に沿わない場合や迅速な改善が難しいことがありますが、自社運営であれば包装プロセスを自由にカスタマイズし、必要に応じて改善を回すことが比較的容易です。
(3)柔軟な対応が可能になる
パックセンターを自社運営するメリットに柔軟な対応が可能なことがあります。例えば、お盆や年末年始のようなイベントなどで特別な包装に差し替えて大量に必要になる場合です。
他にも花火大会などで一部地域でのみ需要が一時的に急増する場合でも、該当店舗に包装作業のための余分な人員を投入することなく対応できます。よって、パックセンターでの柔軟な対応は労働コストの抑制にもつながります。
4.パックセンターを外注利用するリスク
パックセンターを外注利用する場合は設備や人材教育などの初期投資をすることなく高い品質の包装を利用できますが、以下のリスクがあります。
- コストが増加するリスク
- 品質管理が外部依存のリスク
それぞれご紹介していきます。
(1)コストが増加するリスク
パックセンターを外注利用する場合、内容が単純で数量が一定であれば大きなコスト増加は避けられます。しかし、特別な依頼が発生した場合にはコストが増加するリスクがあります。例えば、イベント向けの複雑な包装や、少数ロットでの特注品、特急対応などは通常より割高となっていることがあります。
さらにパックセンターの契約に含まれていないオプションを追加したい場合や、予期せぬ需要変動によって何度も依頼内容を変更したい場合は、予算を超える可能性があります。これに加え、急な変更に伴う手数料や納期の遅延が発生することも考えられ、結果的に全体のコストがさらに膨らむ可能性があるため、包装依頼内容について慎重な計画が求められます。
(2)品質管理が外部依存のリスク
パックセンターの外注利用は、設備や人材教育などの初期投資をすることなく高い品質の包装を利用できます。しかし、それは品質基準を外部業者に依存するということです。品質管理が外部に依存していると、包装のばらつきや作業中のトラブルが発生しても、即座に対応することが難しく、顧客満足度の低下につながる可能性があります。
自社商品の品質基準を維持するには、定期的な品質監査やコミュニケーションが必要となります。また、外部業者の変更やトラブルが生じた際には、製品の供給が滞るリスクもあるため、長期的には自社内での品質管理体制の構築を検討することが望ましいでしょう。
5.パックセンターを自社運営する場合のおすすめ製品
パックセンターを自社で運営する際、作業効率を上げるためには導入する機器選びが重要となります。以下の青果物の袋とじ作業を自動化できる機器を紹介します。
- マックス 自動搬送袋とじ機
- マックス袋とじ機 コニクリッパ
- マックス袋とじ機 エアパックナー
- マックス袋充電式袋とじ機 モバイルパックナー
それぞれ紹介します。
(1)マックス 自動搬送袋とじ機

マックスの自動搬送袋とじ機は、特に青果物の包装作業において高い効率を実現する優れたソリューションです。この機械は、野菜や果物が入った袋を機械にかけるだけで、自動的に袋口をカットし、結束を行います。幅広い種類の野菜や果物に対応でき、1分間に最大44袋を処理する高いパフォーマンスを誇ります。自動搬送機能も備えており、ベルトコンベアによる袋の自動搬出が可能です。
食品業界では、人件費の高騰への対応や作業効率の向上が常に求められていますが、この製品は操作が簡単で、少ない人手でも大量の作業を自動化することができます。
マックス 自動搬送袋とじ機について詳しくはこちら
(2)マックス袋とじ機 コニクリッパ

マックスのコニクリッパは、青果物や食品を袋詰めする際の結束作業を大幅に効率化するコンパクトな袋とじ機です。この機械は、袋に入れた商品を軽くひねって差し込むだけで、瞬時に結束が完了するというシンプルな操作性が特長となります。ネットやポリ袋のどちらにも対応しており、袋口のカットも可能なので、柔軟な使い方ができます。
この製品は1袋あたり約0.4秒で結束を完了し、1分間で20〜25袋の作業が可能です。中小規模の企業にとって、短時間で効率的に作業を進められるため、作業時間の短縮とコスト削減に役立ちます。
マックス袋とじ機 コニクリッパについて詳しくはこちら
(3)マックス袋とじ機 エアパックナー

マックスのエアパックナーは、マックスが提供するエアーを動力とした袋とじ機で、特にネット袋やポリ袋を使用した青果物の包装作業に適しています。この機械は、袋を機械に差し込むだけで瞬時にクリップ結束が完了するため、手間のかかる作業を大幅に簡略化します。また、青果用のエアパックナーは1巻で最大12,000回の連続作業が可能で、長時間の使用にも耐えられる設計です。
マックス袋とじ機 エアパックナーについて詳しくはこちら
(4)マックス充電式袋とじ機 モバイルパックナー

マックスのモバイルパックナーは、持ち運びやすいコンパクトなデザインで、手軽に袋とじ作業を行える充電式の袋とじ機です。わずか6.5キログラムの軽量設計で、電源がない場所でもフル充電で最大5,000回の結束作業が可能です。このため、場所を選ばずに利用でき、小規模な生産現場や移動が多い現場に非常に適しています。
ネットやポリ袋のどちらにも対応しており、袋口のカット機能も搭載されているため、簡単かつ効率的に袋とじ作業を行えます。また、導入コストも比較的低いため、小規模な生産体制を持つ企業でも導入しやすいのが特徴です。コストパフォーマンスに優れ、現場での柔軟な運用が求められる企業に適している製品となります。
マックス充電式袋とじ機 モバイルパックナーについて詳しくはこちら
パックセンターに導入する袋とじ機をお探しの方はマックス株式会社へ
パックセンターの業務効率化を実現する場合には、作業フローを最適化し、現場のニーズに合った機器の選択は欠かせません。マックス株式会社では、パックセンターの運営に役立つさまざまな包装機器を提供しています。青果物の袋とじ作業や自動化を目指す企業にとって、当社の機器は生産性向上と作業負担の軽減を実現し、日常の業務効率化を支援します。
パックセンターに導入する袋とじ機をお探しの方は、ぜひマックス株式会社にご相談ください。
