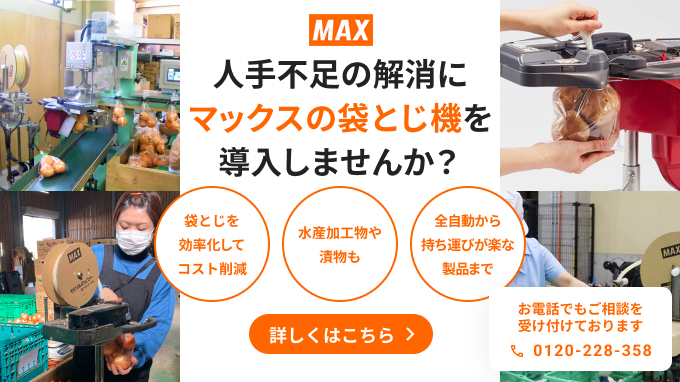省人化が工場にもたらす効果とは?実施時の課題と対策を詳しく紹介

「工場で省人化を進めるとどんな効果があるの?」
「省人化の実現で注意する点は?」
近年、多くの工場や生産現場で深刻な問題となっている人手不足に対して、今注目されているのが省人化です。限られたリソースで効率的に生産を行えるようになるため、労働力の減少や高齢化が進んでいる企業に有効な取り組みとなっています。また、人手に頼らず、工場の自動化や最適化を進めるので、業務効率化の方法として取り入れている企業もあります。
この記事では、省人化を工場で実現するために有効な方法、実施時に必要なプロセスについてご紹介します。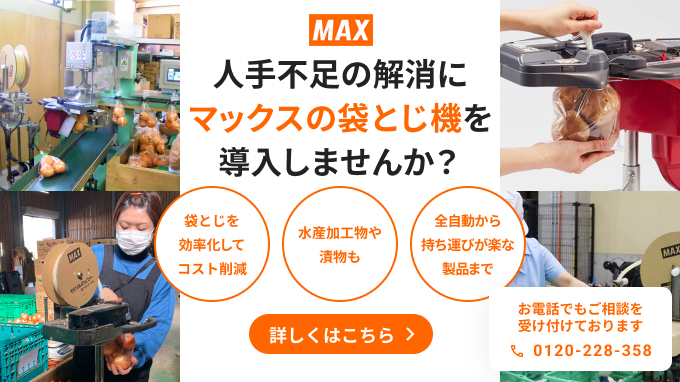
1.省人化とは?業務効率化との違いは?
省人化とは、工場などの現場で人員を減らしながらも、生産能力や品質を維持することを目的とした取り組みを指します。特に、少子高齢化が進む現代社会では、労働力の不足が深刻な問題となっており、企業は限られた人員で生産を維持、向上させる必要があります。このような状況に対応できる取り組みとして省人化が注目されています。
省人化は業務効率化の方法の一つです。業務効率化は作業を効率的に行うために無駄を削減し、時間やコストを最適化することを目指す活動となります。業務効率化は、必ずしも人員削減が目的とは限らず、同じ人数で生産性を向上させることも含まれます。例えば、作業フローを見直し、余計なプロセスを省くことで、生産量を増やすことができる場合もあります。
このように、省人化と業務効率化はどちらも生産性向上を目指すアプローチですが、その主眼点に違いがあります。
2.省人化を工場で実現する技術や方法
省人化を工場で実現する場合、以下のような技術や方法が有効です。
- 作業を効率化できる機械や技術の導入
- ITシステムの活用
(1)作業を効率化できる機械や技術の導入
省人化を工場で実現する場合には、生産ラインで作業をサポートする機械や技術の導入が有効です。特に自動化技術の進化により、組み立て作業、検査、包装など、かつて人の手で行われていた作業が機械によって代替され、手作業への依存を減らすことが期待できます。
例えば、自動搬送システム(AGV)は、工場内での物品や部品の移動を自動化し、従来は作業員が行っていた運搬作業を効率的に行います。これにより、時間と労力が削減され、全体的な作業効率が向上します。
(2)ITシステムの活用
IoTやAI技術の導入は、工場の省人化において重要な役割を果たします。これらの技術を活用することで、工場内の製品やシステムが連携し、リアルタイムでデータの管理や分析が可能になります。
例えば、IoTを使って設備の稼働状況を監視し、必要に応じて自動でメンテナンスを行うシステムを導入することで、停滞時間を最小限に抑えることにつながります。また、AIを活用して生産プロセスを最適化することで、人的介入を最小限にしつつ、生産効率の向上も期待できます。
3.省人化を工場で実現するためのプロセス
省人化を工場で実現するためには以下のプロセスが重要となります。
- 現状の課題分析と改善
- 適切な技術と製品の選定
- 段階的な導入とテスト運用
(1)現状の課題分析と改善
工場の現場における省人化を進めるには、まず現状の課題を正確に把握する必要があります。どの作業工程が時間やコストを多く要しているのか、人員の負担が集中している部分はどこか、どの工程が自動化に向いているかを分析し、改善すべき点を明確にします。生産フロー全体を見直すことで、無駄を排除し、作業の効率化を図ることができ、結果として省人化の実現につながります。
(2)適切な技術と製品の選定
省人化を進める際には、工場の規模や業務内容に応じた最適な技術や製品を選定することが重要です。例えば、大量生産を行っている工場では、ロボットアームや自動搬送システム(AGV)のような大型製品の導入が効果的です。一方、手作業で行っている商品包装や組立て作業には、専用の包装製品や省力化製品が有効です。適切な技術や製品の選定は、コストパフォーマンスの向上にもつながります。
(3)段階的な導入とテスト運用
省人化は、工場全体への導入を一度に実施するのではなく、段階的に進める必要があります。特定の工程やエリアからテスト運用を始め、実際の効果や課題を洗い出しながら、徐々に他のエリアへ拡大が推奨されます。こうした段階的なアプローチにより、省人化の成功率を高めることにつながります。
4.省人化を工場で実施する前に確認すること
省人化を工場で実施する前には、以下のことを確認することで失敗のリスクを減らすことができます。
- 工場や業務ごとに合っている機械や技術か
- 既存の設備との連携ができるか
- 導入にかかるコストと時間
(1)工場や業務ごとに合っている機械や技術か
工場や業務に適した技術と機械を選ぶことは、効率的な省人化を実現するために不可欠です。一つの技術や機械で全工程に対応するのは難しく、小規模な工場から多品種少量生産を行う大規模な工場まで、汎用的な機械や技術が期待通りの成果を生まない場合もあります。
そのため、現状の製造プロセスを詳細に分析し、どの工程に機械化や、さらなる効率が必要かを見極めることが必要となります。また、将来的な拡張性を考慮し、柔軟に対応できるシステムの導入も重要です。
(2)既存の設備との連携ができるか
省人化のために機械や技術を導入する際、既存の設備とのスムーズな連携が生産効率を左右します。特定の工程だけを効率化すると、古い設備やシステムとの不整合が生じ、生産性の低下を招くリスクがあるためです。
これを防ぐには、既存の設備との互換性やアップグレードの可能性を事前に調査し、問題なく連携できるように準備することが重要です。段階的な自動化導入や柔軟なシステムアップグレードは、このリスクを軽減する効果的な方法となります。
(3)導入にかかるコストと時間
工場で省人化を実現するための新しい設備を導入する際には、初期コストや時間の見積もりが重要となります。特に、工場全体の運用に大きな変更が必要な場合、調整期間が長引くこともあるため、スケジュール管理が重要です。また、短期的には設備投資が必要となり、初期費用がかさむことが予想されます。
導入にかかるコストや時間を抑えるには、パイロット導入を一部のラインで行ってから全体に展開したりなど、柔軟な計画を立てることが有効となります。
5.省人化を工場で実施した後に行うこと
省人化を工場で実現するには、実施して終わりではなく、以下のようなことを行うことで効率性を最大化させることができます。
- 導入による効果の測定
- 定期的なプロセスの見直し
(1)導入による効果の測定
省人化を導入した後は、その効果を定量的・定性的に継続して測定することが必要不可欠です。導入前と後のデータを比較し、目標が達成されたかどうか、または改善が必要な箇所を明確にします。
例えば、自動化製品やロボットの稼働率や停滞時間の削減効果を具体的な数値で追跡します。また、生産量や工程速度、不良品発生率なども測定し、変化を定量化することで成果を見える化します。
(2)定期的なプロセスの見直し
省人化の効果を最大限に引き出すには、定期的にプロセスを見直すことが不可欠です。技術は日々進化し、市場のニーズも変化するため、導入したシステムやプロセスが最新の状態で効率的に機能しているかを確認する必要があります。
また、見直したプロセスに従業員が適応できるよう継続的な研修やトレーニングを実施してサポートする必要があります。
6.省人化を進める工場におすすめの袋とじ機
工場で袋とじ作業を行っている場合には、以下のような製品の導入が省人化に有効です。
- マックス 自動搬送袋とじ機
- マックス袋とじ機 コニクリッパ
- マックス袋とじ機 エアパックナー
(1)マックス 自動搬送袋とじ機

マックスの自動搬送袋とじ機は、特に大量生産を行う工場や包装作業が多い現場に適した製品です。この機械は商品を袋に入れ、袋を搬送ヅメに引っ掛けるだけで自動で袋留め作業を行うものです。袋とじ作業を自動化するため、労働コストを大幅に削減しながら、作業効率を最大限に高めることができます。商品の入った袋を搬送ヅメに引っ掛けることで自動で搬送し、袋とじ作業を行う仕組みは、手作業に比べて時間短縮が可能なだけでなく、正確な作業を実現し、不良品の発生を抑えることも期待できます。
マックス 自動搬送袋とじ機について詳しく知りたい方はこちら
(2)マックス袋とじ機 コニクリッパ

マックスのコニクリッパは、特に青果物の袋とじ作業に向いている製品となります。電動タイプで高い作業性能を誇り、スピーディーかつ確実に袋を閉じることが可能です。省スペースの現場でも活用できるため、広い工場だけでなく、小規模な包装エリアでもその効果を発揮します。
特に、コンプレッサを使用せずとも100V電源の使用で利用できるため、手軽に作業時間を短縮できるという点で大きなメリットがあります。
マックス袋とじ機 コニクリッパについて詳しく知りたい方はこちら
(3)マックス袋とじ機 エアパックナー

マックスのエアパックナーは、特に野菜や果物などの包装に適した袋とじ機です。エアコンプレッサを利用して袋を閉じるため、商品の形状や品質を損なうことなくしっかりとパッケージングすることができます。繊細な商品を扱う工場では、手作業では難しい適切な締め具合を自動で行えるため、製品の品質保持に大きく貢献します。
マックス袋とじ機 エアパックナーについて詳しく知りたい方はこちら
工場に導入する袋とじ機をお探しの方はマックス株式会社へ
省人化を進める工場にとって、機械製品の導入は生産効率の向上やコスト削減に大きく寄与します。特に袋とじ作業は多くの現場で行われる重要な工程であり、作業のスピードや精度、製品の品質に直結する部分となります。
省人化に必要なプロセスは現場の従業員と調整することが重要ですが、適切な製品の選定は製品の提供元に相談することが有効です。本記事で紹介したマックスの袋とじ機は、いずれも省人化を実現しつつ、作業の効率化を最大限に高めるために設計されています。
マックスでは代理店様を通してデモ機の貸し出しなども行っておりますので、袋とじ機の導入を検討中の方は、ぜひマックス株式会社にご相談ください。
※マックス袋口結束機「コニクリッパ」・マックス袋口結束機「エアパックナー」・パックナーは、マックス株式会社の登録商標です。