野菜の直接販売の方法とは?ルールやメリット・デメリットを解説

「野菜を自分で販売してみたい」
「直接販売はどのような申請や手続きが必要?」
このように悩まれていませんか。
この記事では、直接販売におけるルールや申請手続きの有無、直接販売の種類を紹介します。
自社にふさわしい直接販売の方法を選択し、正しいルールで直接販売を楽しみながら進めていきましょう。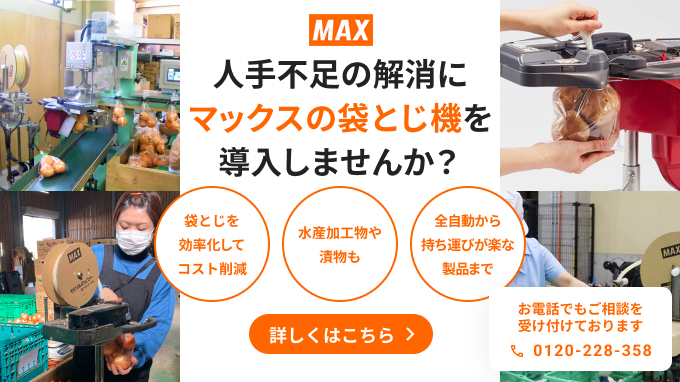
1.野菜の直接販売とは?
野菜の直接販売とは、生産者が消費者に野菜や果物などの生産物を卸売業者などを介入させずに直接販売することを指します。
卸売業者のような買い付けによる販売とは異なり、生産者自身がどのようにどのような形で販売するかを自由に選択することが可能です。
消費者にも、生産者から直接購入することで新鮮で安全な野菜を手に入れられると人気のある販売方法の1つとなっています。
また、野菜の小分け作業や包装に至るまで生産者が対応する必要があるため、直接販売に伴う業務が新たに発生します。
直接販売を行う際は、生産量や販売方法による手間を把握し、規模に見合った方法あるいは生産業務と並行し展開できる方法を検討していきましょう。
2.野菜の直接販売におけるルールと規則
野菜を直接販売する際に守らなくてはならないルールにはどのようなものがあるのでしょうか。
ここでは、販売許可におけるルールと規則を紹介します。
野菜の直接販売におけるルールと規則は、主に以下の2つが挙げられます。
- 自分で栽培した野菜や果物は販売許可の申請は不要
- 自分が生産していない野菜や果物の販売は申請が必要
生産者であるかどうかによって内容が異なるため詳しく見ていきましょう。
(1)自分で栽培した野菜や果物は販売許可の申請が不要
野菜の直接販売におけるルールと規則の1つ目は、自分で栽培した野菜や果物は販売許可の申請が不要であることです。
自分で栽培・生産した野菜や果物を販売する際には、販売許可書の申請は不要のため販売をすぐに始めることができます。
ただし、野菜や果物を調理・加工した場合には、食品営業許可または食品営業届出が必要になるため、加工品の販売を検討されている場合には事前に申請を行いましょう。
また、直接販売に伴い自己所有の農地に新しく倉庫を設置する際には、200㎡以上の大規模なものは農地法4条許可が必要となるため注意が必要です。
農地法とは、農地の保護や権利関係に関する法律であり、農地を守る目的で制定されているため、倉庫の設置を行う場合には、農地法に基づき申請しましょう。
(2)自分が生産していない野菜や果物の販売は申請が必要
野菜の直接販売におけるルールと規則の2つ目は、自分が生産していない野菜や果物の販売は申請が必要であることです。
自分が生産していない野菜や果物を販売する場合、2021年6月より届出が必要になり、市場からの仕入れはもちろん、生産者から直接仕入れる場合も届出が必要です。
生産していない野菜や果物を販売するためには「野菜果物販売業」の届けが必要であり、さらに届出の項目には食品衛生管理責任者の氏名記入が必要です。
そのため、販売に必要な野菜果物販売業の届出をするには、食品衛生管理責任者の資格取得が必要となります。
食品衛生管理責任者の資格は、1日の講習で取得が完了できます。
3.野菜を直接販売する方法
野菜を直接販売する方法には、以下の7つがあります。
- 無人販売
- 直売所
- 移動販売
- 自動販売機
- 農協
- 道の駅
- ネット販売
それぞれの販売方法を以下で詳しく解説します。
(1)無人販売
1つ目の野菜を直接販売する方法は、無人販売です。
無人販売は、自宅や敷地内などの場所に野菜などの商品を陳列し、お客さんが自分で商品を選んで、その商品に対応する金額を支払う仕組みです。
無人販売には以下のような特徴があります。
- 無人のため営業対応が不要
- 無人のため盗難の恐れや売上金に差額が生じやすい
販売業務は、生産物の設置と集金のみであることから販売にかかる人材確保の必要はなく、敷地のある方や少量の野菜を販売したいと考える方におすすめの方法です。
(2)直売所
2つ目の野菜を直接販売する方法は直売所です。
直売所とは個人で販売箇所を設置し販売する方法です。個人の保有する敷地内であれば販売許可の届出は不要のため、個人営業をしたいと考える方におすすめです。
直売所には以下のような特徴があります。
- 自身が対応できる範囲・規模での販売所の設置が可能
- 集客を見込むためには工夫が必要
お店の規模に関わらず、お客さんとコミュニケーションを取りながら販売を楽しめる点が直売所の魅力です。
生産物を直接手渡しで生産者に届けたいと考える方や消費者のニーズや要望を取り入れたお店づくりをしたいなど営業やお店づくりに力を入れたいと考える方に最適な方法です。
(3)自動販売機
3つ目の野菜を直接販売する方法は、自動販売機です。
自動販売機とは、飲料自販機同様に無人で販売できる方法で、初期費用が掛かりますが、保有する敷地に設置するだけで販売を開始できます。
自動販売機には以下のような特徴があります。
- 24時間365日体制で販売が可能
- 冷蔵機能対応の自動販売機なら暑さに弱い生産物も新鮮なまま販売が可能
- 盗難の恐れが少なく、売上の差額が生じにくい
商品を綺麗に保管でき鮮度の高い商品が届けられる点が自動販売機の魅力の1つです。
無人販売を希望しているが、集金状況や保存状況の管理を徹底したいあるいは非接触での販売方法を取り入れたいと考える方におすすめの方法です。
(4)移動販売
4つ目の野菜を直接販売する方法は、移動販売です。
移動販売とは、軽トラや移動販売車を活用し様々な場所で販売する方法を指し、移動販売の場合、販売する場所によっては事前の許可取りが必要です。
移動販売には以下のような特徴があります。
- 一定の場所にとどまらず、様々な地域の消費者に届けることができる
- 事前に販売許可や申請が必要となる
移動販売には、地域やエリアにしばられないという利点があります。
販売の申請手続きや許可取りなどの手間はかかる一方、ワークショップやイベントへの出店も可能であり、コミュニティが広がるため多くの人と関わりながら事業を展開していきたいと考える方におすすめの方法です。
(5)農協
5つ目の野菜を直接販売する方法は、農協です。
農協は、栽培した野菜や果物を持ち込み販売してもらう方法で、持ち込んだ生産物は全量買取をしてもらえるため、まとまった収入が確保できます。
農協には以下のような特徴があります。
- 全量買取のためロスや廃棄が軽減できる
- 農協による品質審査を受ける必要がある
- 金額の設定は農協により決定され、市場により価格変動が見られる
農協は品質審査があるため、品質が保証されているという消費者の信頼度も高く、初めての販売であっても消費者が手に取りやすいという利点もあります。
まとまった量の生産物の販売を検討している方や金額の設定などを検討するのが困難な方に適した方法です。
(6)道の駅
6つ目の野菜を直接販売する方法は、道の駅です。
道の駅とは、一般幹線道路に設けられた駐車場付きの休憩施設である道の駅で販売することを指します。各地方の道の駅により販売方法や買取方法は異なります。
道の駅には以下のような特徴があります。
- 観光や仕事で訪問した全国各地の人々に購入してもらえる
- 販売手数料が発生することがある
全国各地そして、幅広い世代の手に触れ目に触れられるという道の駅ならではの利点があります。
そのため、地元の消費者だけではなく自社の生産物を全国に広めたいと考える方におすすめの方法です。
(7)ネット販売
7つ目の野菜を直接販売する方法は、ネット販売です。
ネット販売とは、ネットワーク上で展開するフリマアプリや直接販売のプラットフォームを活用し販売する方法を指します。
ネット販売には以下のような特徴があります。
- 時間や場所にとらわれず販売できる
- 自身で包装する必要がある
- ネットやサイトの集客に工夫が必要である
商品の展開方法や打ち出し方など営業力により売上を伸ばすことができる点がネット販売ならではの利点といえます。
ネット環境のある方や好きな時間や空いている時間を活用し、販売を展開していきたいと考える方におすすめの方法です。
4.野菜の直接販売におけるメリット3つ
野菜の直接販売におけるメリットは以下の3つです。
- お客さんや消費者の声を聞ける
- 農協や組合とのつながりができる
- 販売の機会を増やせる
それぞれの項目を以下で詳しく解説します。
(1)お客さんや消費者の声を聞ける
1つ目の野菜の直接販売におけるメリットは、お客さんや消費者の声を聞けることです。
卸業者を使わずに直接販売することでお客さんの生の声を聞くことができます。
生産業だけでは見えなかったニーズや希望を発見できるため、生産物の品質向上に大きく貢献するといえます。
また、直接販売でお客さんと触れ合うことで根強いファンを獲得できるため自社の生産物の口コミを広めてくれるなど広告宣伝効果を期待できます。
(2)農協や組合とのつながりができる
2つ目の野菜の直接販売におけるメリットは、農協や組合とのつながりができることです。
直接販売では、生産者自ら販売所に出向くため他の農家や農協とのつながりが生まれ、新たな出荷先や思わぬ購入先との巡り合わせがあるなどの機会に恵まれます。
さらに、市場や出荷の傾向を把握できるため生産や販売に役立つなど、農協や組織とのつながりは事業の拡大や安定に必要となる情報やコネクションの獲得が期待できます。
(3)販売の機会を増やせる
3つ目の野菜の直接販売におけるメリットは、販売の機会を増やせることです。
直接販売は、場所や時間を選ばないことから、マルシェやインショップ、ネット販売など販売先の選択肢が豊富に備わっているため、販売の機会が増える点が魅力です。
販売の機会が増えることは売上に直接的に働きかけるため、利益向上が期待できます。
さらに、直接販売は事業規模にとらわれることなく、少量からでもすぐに始めることができるため初めての販売でも気軽に挑戦できます。
自社にあった販売方法で、利益の確保を目指しましょう。
5.野菜の直接販売におけるデメリット3つ
野菜の直接販売におけるデメリットは以下の3つです。
- 価格競争に陥りやすい
- 販売先の増加により業務内容が増える
- 人手不足による作業の負担が懸念される
それぞれの項目を詳しくご紹介します。
(1)価格競争に陥りやすい
1つ目の野菜の直接販売におけるデメリットは、価格競争に陥りやすいことです。
直接販売は、販売価格を自ら決定することができる点が直接販売の魅力でもありますが、直接販売を行う生産農家や販売所が隣接している場合、価格競争に陥るリスクがあります。
お客さんは価格の安い方を手に取りやすい傾向にあるため、隣接する直接販売店の価格が自社の価格よりも低価格である場合には、お客さんを呼び込むため味や品質、ブランディングなど価格以外の価値を提供するか価格を下げるなどの必要性に迫られることもあります。
価格競争に陥った場合は、販売実績があがっても利益が出にくくなることもあります。
直接販売を行う際には、近隣の直接販売の設定価格や販売エリアをリサーチし、目標売上や直接販売の目的に見合った方法を選択し、価格競争を回避する必要があります。
(2)販売先の増加により業務内容が増える
2つ目の野菜の直接販売におけるデメリットは、販売先の増加により業務内容が増えることです。
直接販売では、生産者の手によって小分け作業や包装を施す必要があり、生産作業以外にも販売するまでに必要な業務内容の増加が考えられます。
販売方法によっては、販売数の確認や売上にかかった費用計上なども複雑化することから販売による業務内容を事前に確認しておくことが重要です。
(3)人手不足による作業の負担が懸念される
3つ目の野菜の直接販売におけるデメリットは、人手不足による作業の負担が懸念されることです。
直接販売は、気軽に始められる一方、収穫から販売までの工程を自社で担う必要があります。
そのため、簡略化や効率化を図る方法や手段を検討しておくことが、限られた人材で直接販売を成功させるポイントとなります。
現状の業務負担を考慮し、自社が対応できる範囲での販売手段や効率化の方法を検討し、人材不足による作業負担への対策を取っておきましょう。
野菜の直接販売はマックス製品で簡単袋とじ
野菜の直接販売は、少数ロットから始められる手段であることがわかりました。
生産者の手によって届けられる農作物は、消費者にとっても安心して購入できる販売方法としても人気を高めています。
マックス株式会社は、生産者と消費者をつなぐため小分けや包装における工程をスムーズにするサポートを行なっています。
マックス製品で簡単に袋とじを行い、直接販売における業務軽減を目指していきましょう。
